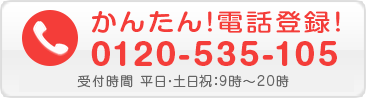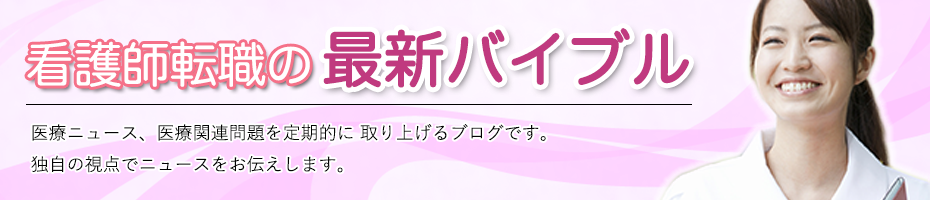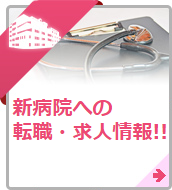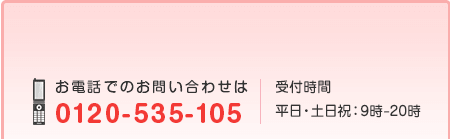現状の社会制度がつくられた時代の背景とそれ以降の時代の変化
こんにちは!ローザスの小澤です。
涼しいを通り越して、寒くなってきましたね。
みなさん、ご自愛くださいね。
久しぶりに私の当番が回ってまいりました。
シリーズとして書かせて頂いております「社会保障制度の今後」、
前回は「Ⅰ.社会保障制度の基本的な考え方」と「Ⅱ.現状の制度について見ていきました。
今回は下記の点について見ていきたいと思います。
Ⅲ.現状の社会制度がつくられた時代の背景
Ⅳ.それ以降の時代の変化
それでは、さっそくⅢの現状の社会制度がつくられた時代の背景にいきましょう。
厚生労働省のHPでは、戦後社会保障制度史というページにて、
今日に至るまでの社会保障制度を簡潔にまとめています。
こちらによりますと、今日の日本の社会保障制度体系が整えられたのは昭和30・40年代です。
この時代に、国民皆保険・皆年金を実現しています。
また、年金給付額の改善や老人医療費の無料化がなされ、
社会保障制度は大幅に拡充されました。
看護学校の数も増え、看護師の数が増加し始めたのもこのころ。
この流れの中がいまも続き、看護師不足=看護師の求人がたくさんある状況を作りだしたわけです。
その後、いくつかの改正がありますが、
制度上の大きな変化は2000年の介護保険制度の開始ということになります。
ですので、まず現在の社会保障費の2大支出先である、
医療・年金の制度がつくられた昭和30・40年代の時代について考えてみましょう。
まずすぐに思いつくのが高度経済成長期にあたるということです。
厚生労働省も今日盛んにアピールしていますが、
社会保障はその財源を抜きには考えられません。
高度経済成長に伴い税収が増加していた中で、現在の制度はつくられているということです。
次に年代別人口の構成です。
生産年齢の人口(15歳~64歳)はこの時代、右肩上がりで増えています。
伸びとしては高齢化率を上回る勢いで、
人口ピラミッドはいわゆるつりがね型に近い形です。
若い人が多ければ、当然病気にかかる方も少なく、
医療保険も収入のほうが支出よりも少ないことになります。
また、家族のあり方も大きく異なっています。
当時は三世帯が大きな割合を占めており、
徐々に二世帯・核家族へと移行していくような段階でした。
さらに医療、介護の必要な高齢者の多くは三世帯で暮らし、
息子の嫁にケアをしてもらうという状況が続いていたわけです。
ここでも負担は家族によってなされていた
=社会全体で保証するコストは低かったわけです。
最後に雇用環境の変化があります。
この時代はいわゆる「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」といった、
日本型雇用慣行といわれる制度が企業で形成されていきました。
基本は正社員であり、さらに右肩上がりで企業が成長しているため、
保険額の負担はそこまで大きく感じられず、しっかりと払ってくれる、
つまり社会保障費の担い手が厳然といたわけです。
まとめると、
①高度経済成長期=社会保障の財源は拡大
②生産年齢人口割合が高い=社会保障の支出は少な目
③高齢者は三世帯がメイン=社会保障の担い手はまだ家族
④正規雇用が中心=社会保障の財源が堅固
の時代だったということになります。
いずれにしても、当てはまるのは、
「社会保障費の財源が拡大し、堅固だった時代に
現在の社会保障制度の大元はつくられている」
ということです。
さて、続いてⅣ.それ以降の時代の変化についてです。
最初に分かりやすくまとめて言えば、上記の時代状況が大きく変化し、
社会保障制度の前提が崩れてしまったということです。
①から④に沿って一つずつ見ていきましょう。
①の高度経済成長はご存知の通り、昭和40年代後半に終焉し、
安定成長の時期に入ります。
それ以降、バブル経済の崩壊を経て、低成長期へと移行。
再度爆発的な成長は見込めない時代となってきています。
②の生産年齢人口割合ですが、同じく昭和40年代後半から横ばい、
続いて平成に入ると減少傾向に入りました。
少子化傾向も、いまだ歯止めがかかりません。
逆に高齢化率は増加を続け、さらに割合が拡大していくことが見込まれています。
③の高齢者の三世帯ですが、その後は減少を続け、
逆に単独世帯と夫婦のみの世帯という高齢者のみ世帯と、
平成4年に入ると逆転します。
④の正規雇用に関しては、統計がはじまった昭和50年代から、
ずっと割合としては減り続けています。
つまり、派遣やパートなどの非正規雇用の割合がずっと増えているわけです。
つまり、数字に沿って変化をまとめると、
①経済成長の停滞=社会保障の財源は拡大しない
②少子高齢化=社会保障支出が増大
③高齢者単独世帯の増加=社会保障の担い手としての家族の崩壊
④非正規雇用の増加=社会保障の財源が不安定化
ということになります。
改めて考えてみると、ここ40年に過ぎない間に、
とても大きな変化を経験しているのですね。
さあ、いよいよ次回以降、こういった時代の変化に対して、
政府はどのような手を打とうとしているのか、
「社会保障制度改革推進法」に沿って見ていきたいと思います。
株式会社ローザス
2013年10月22日カテゴリー:医療全般
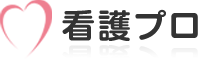
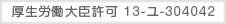
![[厚生労働大臣許可 13-ユ-304042]0120-535-105(受付時間 平日・土日祝:9時-20時)「友人にも紹介したい」率なんと97.6% *2013年度4月当社集計](https://www.kango-pro.jp/rozasnews/wp-content/themes/kango-pro/images/hd_tel.png)